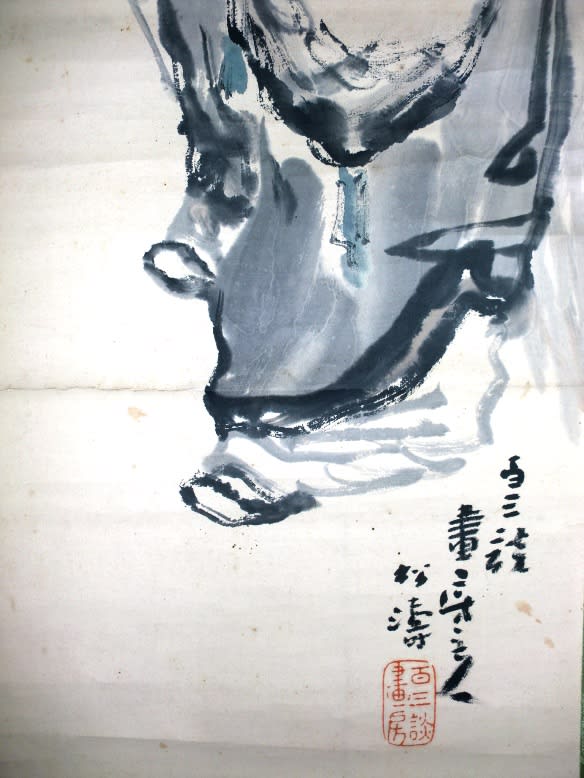昨夜は赤坂、今夜は再び大宮・・、長男を風呂に入れている時間が無い・・・。
さて本日は久しぶりに南画の世界。
釧雲泉、桑山玉洲、そして菅井梅関・・・、贋作多い南画家の作品はまるで迷路のようです。菅井梅関の作品もなんだかんだと四作品目となりました。
冬景獨釣図 菅井梅関筆 その4
絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 合箱
全体サイズ:縦2230*横692 画サイズ:縦1340*横555
![]()
魑魅魍魎たる南画の世界、江戸期から第2次世界大戦後までの贋作横行の時代、まさしく贋作は貧しさの象徴のようです。
![]()
作品の題名は仮題です。
![]()
郷里を思い起こさせる雰囲気があります。
![]()
木々の描き方がうまいですね。
![]()
印章は「菅井之印」の朱文白方印と「梅関之印」の白文朱方印の累印が押印されています。
![]()
![]()
作品をどこまで愉しめるか、そこがキーポイントですね。
さて本日は久しぶりに南画の世界。
釧雲泉、桑山玉洲、そして菅井梅関・・・、贋作多い南画家の作品はまるで迷路のようです。菅井梅関の作品もなんだかんだと四作品目となりました。
冬景獨釣図 菅井梅関筆 その4
絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 合箱
全体サイズ:縦2230*横692 画サイズ:縦1340*横555

魑魅魍魎たる南画の世界、江戸期から第2次世界大戦後までの贋作横行の時代、まさしく贋作は貧しさの象徴のようです。

作品の題名は仮題です。

郷里を思い起こさせる雰囲気があります。

木々の描き方がうまいですね。

印章は「菅井之印」の朱文白方印と「梅関之印」の白文朱方印の累印が押印されています。


作品をどこまで愉しめるか、そこがキーポイントですね。










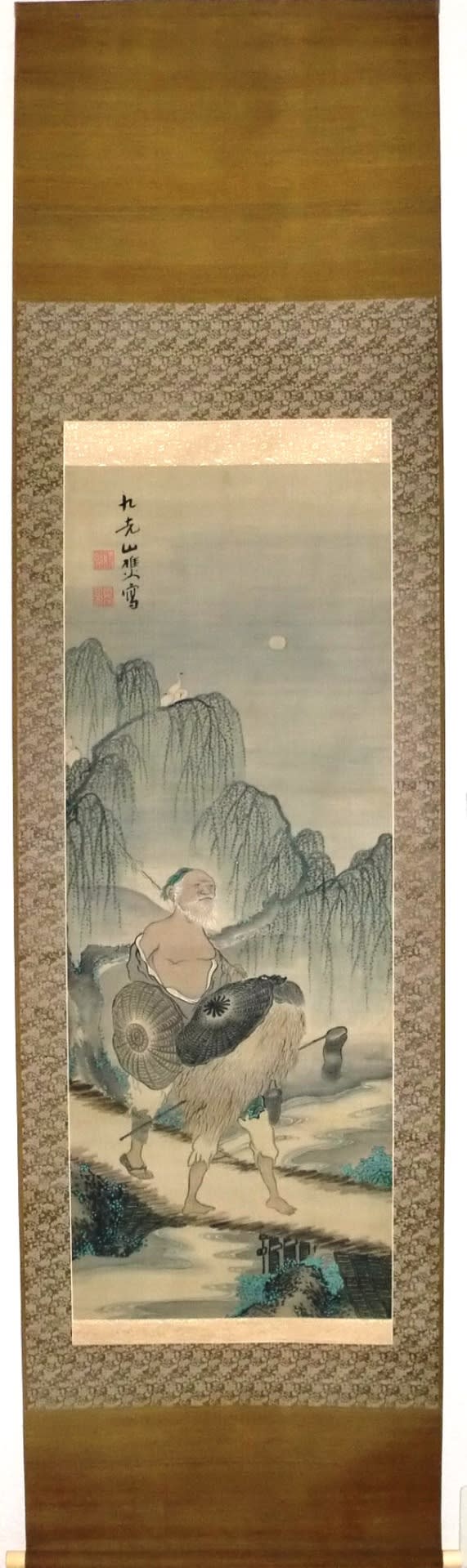


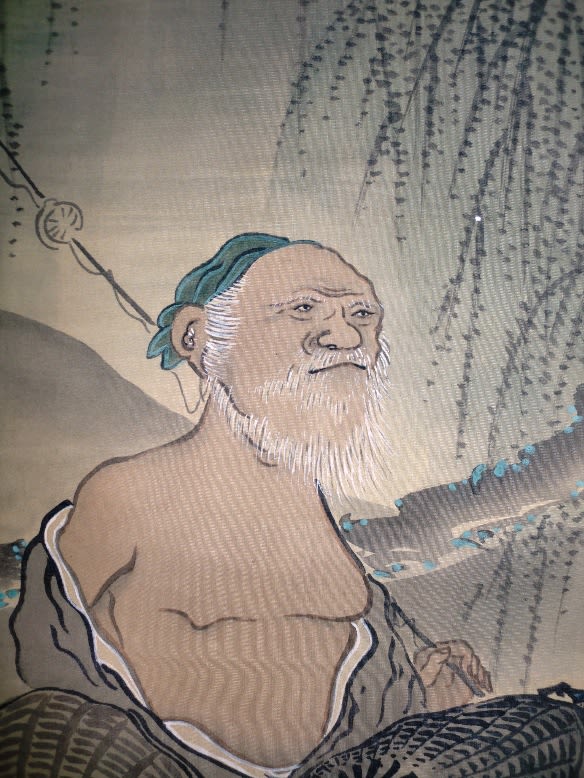



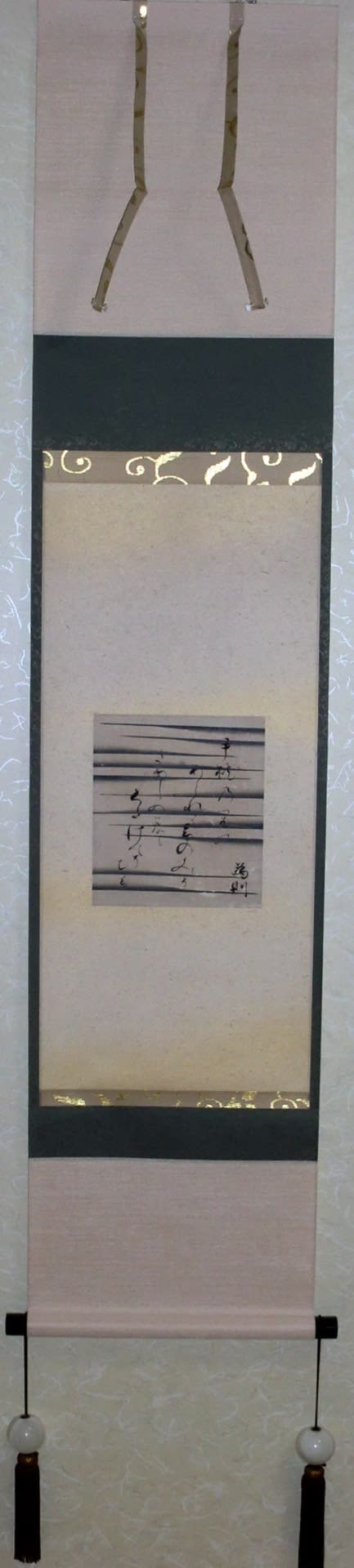

















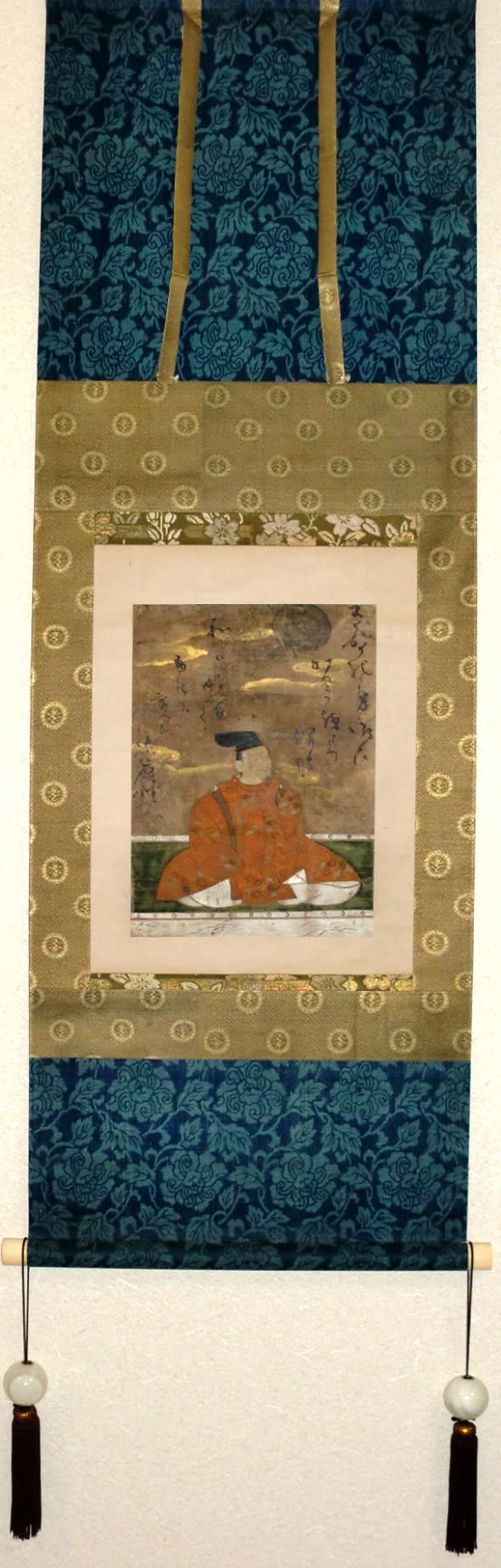

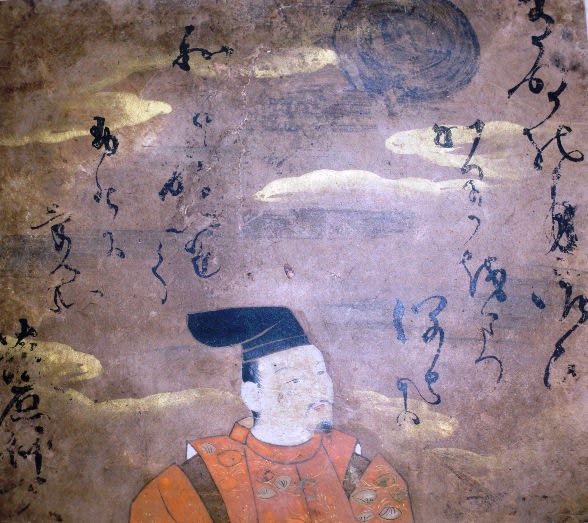



























 福田豊四郎のこのたびの作品は如何?
福田豊四郎のこのたびの作品は如何?